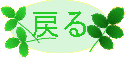
真っ赤な夕日を見ると思い出す。
あの日、異常なほどに赤かった夕日の光を。
その光に照らされて赤くなった部屋を。
その部屋で母が着てた赤いシャツを。
その母から流れ出た赤い血を。
赤い記憶
今日の太陽は、赤かった。でも、あと2時間もしないで日没だろう。
傾きだした太陽を見ながら光子は思った。
窓から目を離し、教室を見回してみた。
6時間目ということもあり、大半は光子と同様に授業を聞いていないものが多かった。
居眠りをしているもの、友達としゃべっているもの、お菓子か何かを食べているものさえいる。
そんな彼らが赤く見えた。
赤い太陽の光によって教室中が赤一色に見えた。
光子は、また窓に視線を戻し夕日を見つめた。
それにしても赤い。赤すぎる。
まるで、あのときのような赤さだ。
あの日の夕日もこんな風に赤かった。
あの日、学校から帰ってきたまだ9歳だった私を母はどこかへ連れて行こうとした。
「お母さん、どこへ行くの?」
「黙ってついてくればいいんだよ。」
また”あれ”に連れてかれると直感的に思って私は抵抗した。
「お母さん、私行きたくない。」
もう嫌だった。”あんなこと”されるなんて。
「誰がお前を今まで育ててきたと思ってるんだよ。」
ばしっ
母は私を殴りつけた。
私は、部屋に倒れこんだ。
とても痛かった。
口からも血が出てた。
でも、もう”あれ”に連れてかれるのは絶対に嫌だった。
私はとっさに出しっぱなしで近くに置いてあった包丁を手に取った。
「そんなもんでなんになんだよ。刺せるもんなら刺してみな。さぁ、行くよ。」
母が私の腕をつかんで、立たせようとした。
「いや!!」
ずぱっ
包丁を持っていた腕を振り回したら母の首を切り裂いていた。
「あっ、お母さん!?お母さん?」
どろどろと倒したコップから水が流れるように母の首から血が流れ出てた。
部屋の中は、夕日の赤い光と母の赤い血で赤く染まってた。
「光子、これから比呂乃と遊び行くんだけど、一緒に行かない?」
帰りのHRが終わり、帰ろうとしてた光子に好美が話しかけてきた。
「悪いけど、今日は遠慮しとくわ。」
「えっ、どうして。なんか用あるの?」
「別に。ただ、今日は1人でいたいのよ、じゃあね。」
そう言って、光子は好美に背を向けて教室の出口へ歩き出した。
背後から好美の「また、明日ね。バイバイ」と言う言葉が聞こえたが振り向かず教室を出た。
カンカンカン
気がつくと、光子は、あるアパートの階段を登っていた。
階段を上りきると、一番奥の部屋の前で立ち止まった。
人が殺されたこともあって、この部屋はずっと空き家だった。
この部屋は、光子が母と暮らした場所であり、同時に母を殺した場所でもあった。
こんな部屋2度と来たくはなかった。
しかし、赤い夕日を見た後は、なぜか足がここへ向いてしまう。
入りたい。中に入りたい。
光子は、無性にこの部屋に入りたくなっていた。
かばんの中から1つの鍵を取り出し、部屋のドアのぶに入れてみた。
あまり家に帰らなかった母が小さな光子に渡したこの部屋の鍵だった。
だけど、鍵は合わなかった。
光子がこの家から出たときに鍵は変わってしまっていた。
それでも、光子は何度も何度も合わない鍵をドアノブに入れた。
開きもしないドアの前で合わない鍵をドアノブに入れ続けた。
真っ赤な夕日の光の中、光子は開かないドアの前で立っていることしかできなかった。
真っ赤な夕日を見ると思い出す。
あの日、異常なほどに赤かった夕日の光を。
その光に照らされて赤くなった部屋を。
その部屋で母が着てた赤いシャツを。
その母から流れ出た赤い血を。
そして、夕日の光の中で母の血と混ざって赤く染まった自分の涙を・・・・・